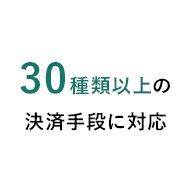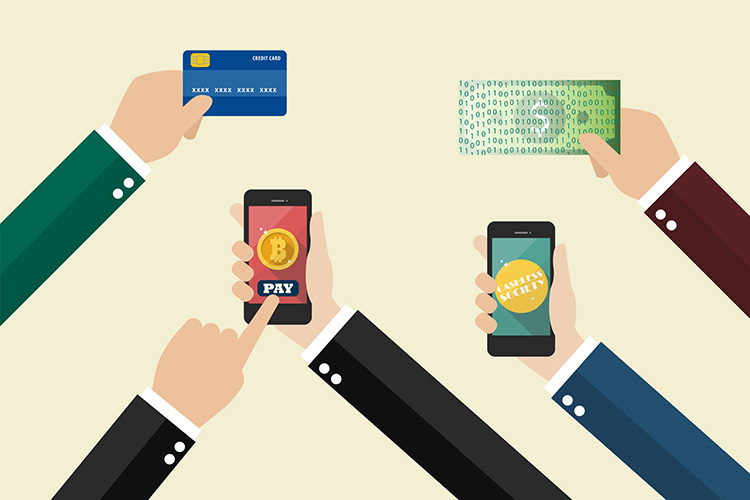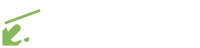Powered by 三井住友カード
「ペイサポ」は三井住友カードがお届けする、決済サービス・決済端末の情報メディアです。
決済サービスや端末を導入する際の基礎知識からメリットについて、丁寧に解説します。
新着記事
目的別に記事を探す
目的別に記事を探す
店舗経営者の方へ
豊富なキャッシュレス決済に対応!
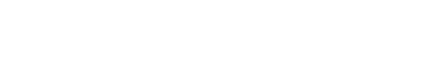
その他おすすめ記事サイト
キャッシュレスの基礎知識やキャッシュレス決済の導入方法など、キャッシュレスに関する最新情報を丁寧に解説します。
経営者・個人事業主・スタートアップの担当者が知っておきたいバックオフィスの基礎知識をご紹介しています。
その他おすすめ記事サイト
キャッシュレスの基礎知識やカード活用術、お困りごと解決情報など役立つ情報を発信しています。
経営者・個人事業主・スタートアップの担当者が知っておきたいバックオフィスの基礎知識をご紹介しています。
店舗経営者の方へ
豊富なキャッシュレス決済に対応!
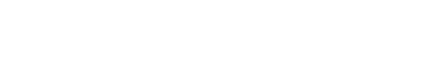
その他おすすめ記事サイト
キャッシュレスの基礎知識やカード活用術、お困りごと解決情報など役立つ情報を発信しています。
経営者・個人事業主・スタートアップの担当者が知っておきたいバックオフィスの基礎知識をご紹介しています。
- 三井住友カード
- 加盟店サイト TOP
- お店がはじめるキャッシュレス決済 トップ
決済サービス・決済端末を導入する際の基礎知識からメリットを丁寧に解説します。三井住友カードプレゼンツ「ペイサポ~お店がはじめるキャッシュレス決済~」